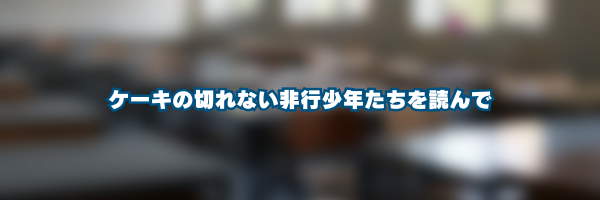読む前、正直に言えば
非行少年たちは「とんでもない悪」で、凶悪で、粗暴な存在だというイメージを持っていた。
しかし、読み進めてすぐに、その考えは崩れていった。
本書では、脳機能の特性や心の状態、虐待だけでなく生活苦など、
さまざまな要因が重なり合い、理解力や行動を制御する力が弱くなっている子どもたちが多いことが描かれている。
普通に会話もできるし、IQが特別低いわけでもない。
一見すると「なぜ?」と思う行動の背景に、複雑な事情があることを知った。
著者は児童精神科医という立場から、
「どんな子どもたちがいたのか」
「この先、どのような支援が必要なのか」
それを社会に伝えたかったのだと感じた。
特に印象に残ったのは、子どもたちのエピソードだ。
多くの子どもたちは、小学生の頃から認められる経験が少なく、
挫折を繰り返し、自信を失ってきたという。
授業には興味を示さないのに、
先生が「今日はお前たちで授業をやれ」と言った瞬間、
みんなが教壇に立ちたがり、教えたがり、答え合わせをしたがる。
その姿に、強く心を打たれた。
教えたい。
頼りにされたい。
認められたい。
これは子どもだけの感情ではない。
大人も同じだと思うし、今の自分自身も、まさにそうだと感じた。
本書の終盤では、現実的な数字も示されている。
非行少年一人あたり、年間約300万円の税金が使われていること。
犯罪による社会的損失が、年間5000億円を下らないこと。
感情論では済まされない現実がそこにある。
自分が直接「支援する側」になれるかと言えば、正直難しい。
でも、せめて無関心ではいないこと。
そして、支えられる側として社会の一部であり続けたい。
この本は、
非行少年をどう見るかではなく、
人をどう理解し、どう関わるかを問いかけてくる一冊だった。